春は寝ても寝ても眠たいトキです🐰
まず、私トキについて・・・
看護師歴10年以上、総合病院、緩和ケア、訪問看護領域の経験があります。
急性期から終末期まで全般的に経験し、今後はフリーランスになることを目標に日々働いています。
今回は「終末期・看取り期」の苦手を克服するためのポインとについてまとめていきます。
終末期の看護は、私自分も苦手分野でしたが、緩和ケアを経験したことで、今では以前より自信を持って向き合うことができるようになりました。
苦手だったからこそ、経験して分かったことが沢山あります。
今でも意識して看護していることなので、共感してもらえたり、少しでも参考になると嬉しいです!
こんな人に読んでほしい!
- 患者さんの看取りを経験し、戸惑っている方
- 患者さんだけでなく、家族との関わり方に困っている方
- 患者さんや家族ともっと自信を持って関わりたい方
終末期の看護について知りたいと思った理由
初めての看取り

私が初めて看取りを経験したのは、総合病院勤務時代の1年目の時でした。
私自身、家族や周囲の方を看取る場を経験したことはなく、全くもって初めての事で、恐怖と不安に押しつぶされそうだった事を覚えています。その時は先輩方がメインに関わるという感じだったので、ひたすら怯えている事しかできませんでした。
 トキ
トキ勤務後友人に泣きつきました。
苦手意識の自覚
独り立ちしてからも3年目くらいまでは、頑張ってはいましたが、自信がなく不安でどうしたら良いのかわかりませんでした。
独特の空気感が苦手で、対応に困っている自分がいることに気がつきました。自覚はしていても、他業務の忙しさもあり向き合おうとはせず、不甲斐なさを感じ、苦手意識は強くなるばかりでした。
転機となったきっかけ


転機となったのは、祖父を亡くした事でした。
私は親族唯一の看護師でしたが、仕事の忙しさを理由に面会にあまり行きませんでした。
正直言うと、近親者の死に直面し戸惑ってしまい向き合おうとしていませんでした。普段の仕事と同じで逃げ腰でした。
ハッとしたのは、祖父が亡くなった後で、今でも大きな後悔の一つです。
家族も同じような思いをしているかもしれないと感じ、私の意識が変わったように思います。
パーフェクトな看護が何かはわからないけれど、興味を持って向き合ってみようと思いました。
前進してできるようになったこと
それから苦手を克服するべく、緩和ケア病棟のある病院に転職して、経験を積みました。
今でも迷うことはありますが、相手と向き合う姿勢には自信を持ってケアができています。
終末期の看護を苦手と思う人の特徴
苦手意識を持っている人の特徴



苦手意識を持つ友人や
私自身の昔の思いを振り返ってみました!
- 患者とその家族との接し方がわからず逃げ腰になっている
- デリケートな場面であり、どのように声をかけたら良いかわからず訪室できない
- 自分の声かけで傷ついてしまうかもしれないと不安で話しかけられない
- 自分自身で苦手である事を意識しすぎて、行動できない
- 最期の時間=悲しい時と思いすぎている
終末期=不安・怖いなどネガティブな感情が連想される現場は、看護する側にとっても大きなストレスです。
患者や家族にとって、人生の大切な場であり、その時間に責任を持つことが何よりストレス源だと思います。
このストレスを乗り越えられなくて看護師を辞めてしまう人もいますし、苦手のままなんとなくやり過ごしている人も多いです。
苦手=ダメな看護ではなく、その時に全力で看護していればそれは良い看護です。
日々頑張っている自分自身を褒めていきましょう!
ここからは、そんな頑張っている自分を、少しでも楽にするべく、『終末期におけるの患者・家族との向き合い方』について説明していきます。
まずは、終末期の考え方と、看護のケア内容についてです。



その状況に置かれた時、何をするといいのかヒントが見えてくると思います!
終末期の看護のケア内容


終末期とは?
終末期といえど、定義は1つではありません。
- 治療が終了し療養期間と切り替わる段階から
- 治療しながらも効果が少なくなってきた段階から
- 余命3ヶ月と推測される段階から
など捉え方はそれぞれですが、一般的には
- 疾患に対しての治療の術がなく、人生最期の時期が迫ったと本人や家族、医療者が感じた時
と言われる事が多いです。
看護師のケアの範囲は?
終末期において、看護師は終末期〜亡くなった後身の回りを整えるまでがケア範囲と考えています。
病院や施設では、患者・家族を見送るまで
在宅では患者・家族の側から離れるまでです。
この期間は、本人の人生の集大成だけでなく、その後の家族の受け止めに影響してくると考えられます。
看護師や医療者は1人では不安だと思うので、周囲の人とも相談・協力しながら介入していきましょう。
ケアの内容は以下に挙げていきます。基本的な視点は4つです。



看護の世界では当たり前のことになりますが、そこに何の意味があるのか理解しておくと行動も取りやすいと思います!
看護師のケアの視点と目的
状態観察
終末期は、
- 症状がありながらも落ち着いて過ごしている時期
- 看取り
- 亡くなった後の時間
と大きく分けて、3つの段階があります。
段階で看護ケアの目的は異なり、
- 落ち着いて過ごしている時期
→本人の苦痛が最小限になるように支援する - 看取り
→本人だけでなく、側で見守る家族も安心できるように支援する - 亡くなった後の時間
→家族が患者の最期を理解し納得できるよう支援する
ケアの対象者が少しずつ変化している事がわかりますが、メインがどちらかという事ではありません。
本人のケアを通して、家族を安心できる環境へと導いていくことが大切です。
バイタルサインや患者の疼痛や倦怠感の増強など身体的な変化をを敏感に捉え、時期が進んでいるサインを感じ取ることが必要です。
メンタルケア
患者は最期が近づくことを、体感として感じている人は多いです。
〈キューブラーロスの受容プロセス〉
否認→怒り→取引→抑うつ→受容
を行き来し、繰り返しながら受容していくと言われています。
状況を受容していても、不安がないわけではありません。
看護師が側で見守っている事は、安心して過ごせることに繋がります。



何かをしようと意識しなくて大丈夫です。訪室し顔を見に行くだけで良いです!
まず相手を気に掛けることから始めてみましょう。
終末期に関わらずですが、患者が今何を感じて過ごしているのか、この先どのように過ごしたいと思っているのかを理解しようとしてみましょう。
信頼関係を築くためのヒントになり、それは同時にメンタルケアに繋がります。
家族ケア
看護師のケアの対象は患者だけではありません。同様に家族もケアの対象者です。
家族にも不安なことは沢山あります。悲しい、辛い思いは患者本人の前では表出できない家族は多いです。
今の日本でも最期=悲しいこととしてタブー視する習慣はあり、家族自身相談できる相手がいない場合もあります。



本人の状況や段階、家族がいない時間の様子を伝えることで、家族の不安や苦痛な思いが少しでも軽減できるかもしれません。
家族の不安の軽減は、患者本人が安心して過ごせる要素にもなります。
最期のケア
看取り期が近づいたとき、患者・家族を安心させられるかは医療者にかかっていると言っても過言ではありません。
患者が苦しまず穏やかに過ごせるように、状態観察・アセスメントをし、適切なケアを行いましょう。
苦しそうにしている時に薬剤を使用するとリスクもあります。リスクを家族へ説明し、相談しながら進めるようにしましょう。家族も段階を理解しながら過ごすことができますし、グリーフケアにも繋がります。
少しでも穏やかに過ごせた時、家族は安心して受容へと向かっていきます。
悲しい感情がないわけではありませんが、少なくとも後悔は減らすことができます。
ここでの声かけや行動が最も苦手と感じるところだと思いますが、意識するポイントを押さえると、怖がらずに向き合うことができると思います!
終末期の看護で意識する5つのポイント
1)患者・家族の今の状態を理解しよう


看護師は状態観察とアセスメント力が必須ですよね!
終末期においても同様で、本人・家族がどのような経過で今に至っているのかを考えてみましょう。
身体状況や精神状態、社会的背景から置かれている状況を理解する事で、看護師も同じ方向を向いてケア介入ができます。
2)患者・家族を知りたいと思おう
私自身の経験になりますが、「どのように声をかけて良いのか、触れて良いのかわからない」を理由に、相手について知ろうとしていませんでした。
そうすると、上辺のケアとなってしまい、無力感や不甲斐なさを感じることとなりました。
緩和ケア病棟では、まず患者・家族を知るところから始めます。そうすると、信頼関係ができてきて、相手から話をしてくれることも多いです。自然と望むことや最期の話もできるようになります。
患者・家族とは業務上の関係ではありますが、そこで向き合うとした時間は、患者・家族だけでなく、看護師本人にとっても、受容の場になります。
逃げている自分より、少しでも向き合えた事を糧にして次に繋げられる自分の方が、仕事人としてカッコよくないですか? 少なからず私はそう思います!
患者・家族と向き合える時間は限られているかもしれませんが、1分でも5分でも気にかける時間を作ってみましょう。信頼関係を築く手がかりが見えてきます。
3)連携のタイミングを理解しよう
終末期において、看護師は家族・医師との連携が不可欠です。
看取りの時期を読む事は難しい時もありますが、早い段階から連携のタイミングについては話し合っておくようにしましょう。
家族との話し合う内容
- どの段階から一緒に過ごしたいと望んでいるのかを把握する
(患者の状態によっては、急に状態が悪くなる可能性があることを医師からも説明してもらう) - 連絡のタイミングについて相談する
- 緊急連絡先を2つ以上は確認しておく
医師との連携について
- 担当医師の終末期の考え方(薬剤使用するのか酸素は増量するのかなど)を知っておく
- 家族へ看取りが近くなっていることをICしているか確認する
- 状態悪化や看取りが近づいたとき、誰にどのタイミングで連絡をしたら良いか確認する



連携のポイントを押さえていると、いざという時少しでも焦らず行動ができます。
4)今後起きることを看護師側から発信しよう
緩和ケア時代から今に至るまで、常に心掛けていることになります。



終末期の場だけでなく、普段の業務でも取り入れています。
看護師側から情報発信することで、信頼関係の構築に繋がります。信頼関係を築く事で、安心感を与えられるだけでなく、業務もしやすくなります。
また、患者・家族と話をするきっかけにもなりますし、相手を理解しようとする姿勢を見せる事ができます!
日々そのように関わっていると、話ができる看護師と思って貰えます。不安や本音を話しやすくなり、情報収集や対応の必要性を考える手段となります。
患者・家族から聞かれた事で、わからないことはうやむやにせず、「わからない」と答えて大丈夫です。(医療的なことは知っておかなければならないこともあるので、全部知らないではダメです)
「わからないです」で終わりではなく、調べたり知っている人に聞いて、しっかりした返答することで、信頼度は上がります。
5)振り返りをしっかりしよう


患者の人生の最期の関わる事は、看護師にも少なからずダメージはあります。
ケアに対する不安や不甲斐なさを感じたり、時には患者・家族に感情移入しすぎて喪失感を感じてしまうこともあるかもしれません。
そんな時に、気持ちの整理をする方法が、デスカンファレンスです。
普段なんとなく行なっていることかもしれませんが、デスカンファレンスの目的として
- 振り返りをすることで、ケアの評価をする
- 意見交換をすることで、知識・ケアの向上に繋げる
- チームで感情を共有することで、医療者のグリーフケアになる
などが挙げられます。
決して意見をぶつけあって、医療や看護をけなすものではありません。
お互いを尊重しながら、良いも悪いも客観的な評価をしていきます。
忙しい時は、5分も時間が取れないかもしれませんが、カンファレンスのメリットは大きいです。
後悔を後に引かないように、気持ちの整理だと思って参加してみましょう。
次の業務に進んでいく為に、一区切りになります。
参加できなくても、議事録などを確認するだけでも良いです!
まとめ
終末期の看護の苦手を克服するポイントについてまとめてきました。
- 誰でも初めての事や経験が少ないと不安は大きい
- 苦手意識を持つ事は悪いことではなく、向き合い方をしれば楽になる。
- ケアに当たるのは一人ではないので、周囲と相談して進めよう
- 患者・家族と信頼関係を築けるように、看護師から情報発信をしよう
- ケアする側にもグリーフケアは必要で、デスカンファレンスで気持ちの整理をしよう
実際の現場には、手術の方、リハビリの方、内科的治療の方などいろいろな理由で療養されている人がいます。終末期の方は、その一人にしか過ぎません。
しかし、終末期のケアは、時に重たくて不安で、大きなストレスになります。向き合い方を考えることで、苦手から少しでも解放されて、気持ちの整理もできやすくなるかもしれません。
その手助けに少しでもなるといいなと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました🐰
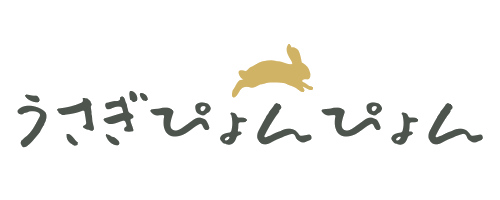
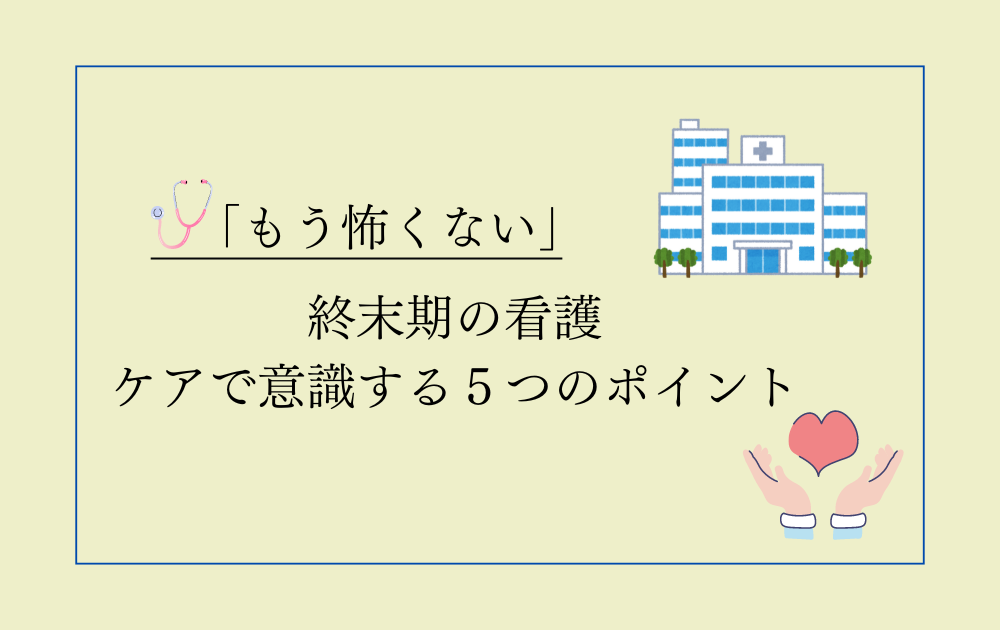


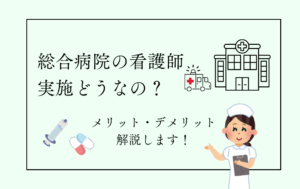
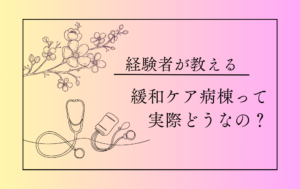
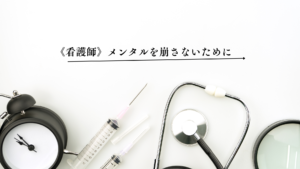
コメント